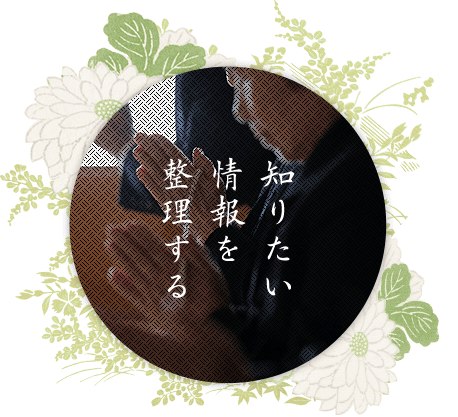三回忌から三十三回忌までの法事・法要
逝去後、100ヵ日を境に、一般的に法要の頻度が変わり、呼び方も変わります。
逝去後100ヵ日までを「追悼法要」、100ヵ日以降を「年忌法要」と呼びます。
【年忌法要(逝去後100ヵ日以降)】
一周忌のみ、翌年の祥月命日(亡くなったのと同月同日)に行い、「満」で数えます。
そして、一周忌以降は「数え」になります。
節目となる「年忌法要」の時期と流れは、以下の通りです。
時期 / 法事・法要名 / 法事・法要の流れ
- 2年目三回忌
- 親族、知人、友人などを招き、僧侶による読経、遺族及び参列者による焼香のあと、精進料理でおもてなしをします。
三回忌は、法要にあたってはひとつの節目となっています。ご案内状を送る人数も、これまでの葬儀や法要などと同じ数となります。
特に三回忌のご挨拶では、皆さまへのお礼を伝えるように努めましょう。
三回忌法要の挨拶例
皆様、本日はお忙しい中、亡き父の三回忌の法要にお越しくださいまして、ありがとうございました。
皆様には、葬儀の折とその後の法要で、ありがたいご厚情を賜り、心からお礼を申し上げます。
日頃はご無沙汰ばかりいたしまして誠に申し訳なく思っております。こうして皆様のお元気なお顔を拝見いたしますと、春の風に吹かれる心地がいたします。父もさぞ喜んでいることと思います。
今日は別室に、ささやかですが、昼食のご用意をいたしました。
どうか、父を偲びながら、ごゆっくりなさってください。
本日は誠にありがとうございました。
本日はお暑い中を、遠路はるばる夫の三回忌にお運びいただき、誠にありがとうございました。
皆様にはお変わりがなく、何よりと存じます。早いもので夫が亡くなりましてもう二年が経ち、私ども遺族も、おかげさまでつつがなく毎日を送っております。
夫が亡くなった時、長男はまだ大学生でしたので、先々のことで思い悩むこともありましたが、皆様から物心両面でのご支援をいただき、なんとか乗り越えることができました。長男は今年の春に大学を卒業して就職しましたので、一安心しております。
気持ちばかりのお膳ではございますが、おくつろぎいただいて、夫の思い出話などをお伺いできればと存じます。
- 6年目七回忌
- 亡くなって満6年の命日に行う法要です。遺族、親族で供養します。
七回忌以降は規模を縮小していくのが一般的です。 - 12年目十三回忌
- 遺族だけで行うのが一般的です。
- 16年目十七回忌
- 遺族だけで行うのが一般的です。
- 22年目二十三回忌
- 遺族だけで行うのが一般的です。
- 26年目二十七回忌
- 遺族だけで行うのが一般的です。
- 32年目三十三回忌
- 遺族だけで行うのが一般的ですが、弔い上げとする場合、大勢を招いて盛大におこなう場合もあります。
三十三回忌または五十回忌を「弔い上げ」として、その後の法要は先祖代々の法要とともに行われるようになるのが一般的です。
弔い上げとは
弔い上げとは、年忌の最後を指して言います。
一般的には三十三回忌や五十回忌がこれにあたりますが、十七回忌、百回忌などを節目に弔い上げとすることもあります。
弔い上げをもって、それ以降の仏事は行わず、年忌法要は終了ということになります。
現代の弔い上げ
仏教においては、三十三回忌には、どんな罪を犯した故人でも、極楽浄土へ行けるようになり、祖先となるという考え方を取ります(※宗派によって異なります)。
一世代の単位が30年であるように、親の弔い上げの頃には、自分も亡くなった親と同世代という場合も多いものです。
また、高齢化が著しい現代の社会では、故人の享年自体が高齢なこともあり、遺族や親戚もまた、高齢となります。そのため三十三年、五十年と年忌を重ねることも難しい現状があります。
そのため、故人を知る人がいなくなったタイミングで弔い上げとするケースも増えています。
弔い上げの行事は、一般的には通常の年忌よりも盛大に行われ、法要の手順や特徴は、宗派、地方によりさまざまな違いがあります。
一般的には仏壇にある戒名の刻まれた位牌を片づけ、先祖代々の位牌に合祀します。
その他の年忌法要
- 7月15日
8月15日お盆 - 親族、知人、友人などを招き、僧侶による読経、遺族及び参列者による焼香のあと、精進料理でおもてなしをします。